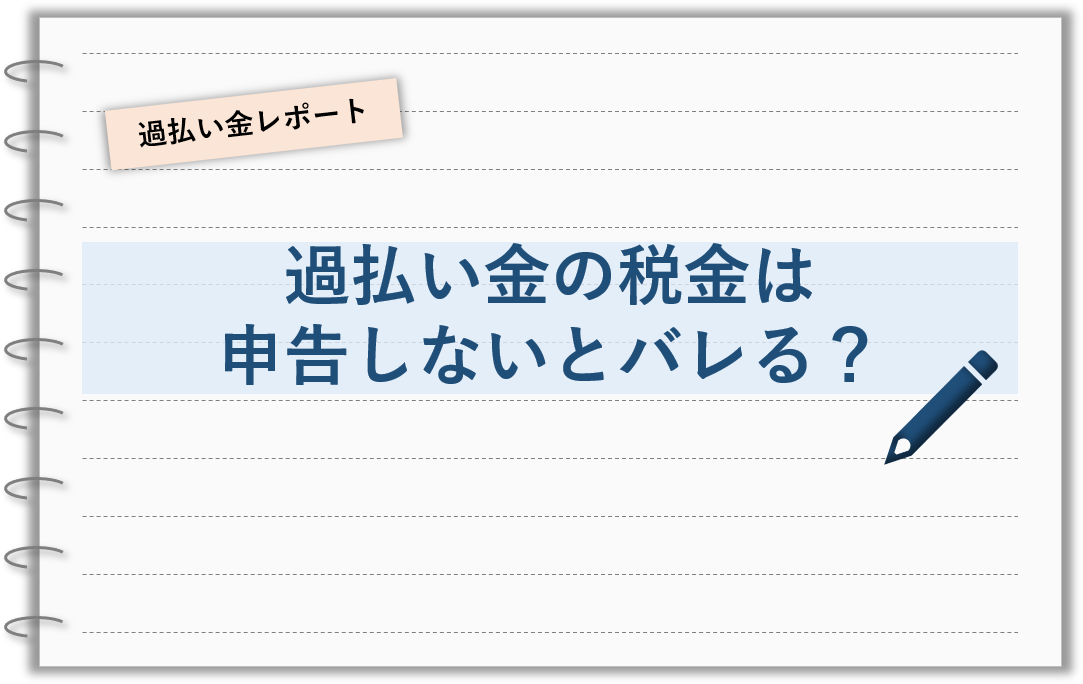戻ってきた過払い金はもともと多く払い過ぎていたお金なので「全て自分の物」と思いがちです。しかし過払い金の元金とともに「利息」も受け取っていると、税金が発生し、確定申告をしなくてはいけない場合があります。
しかしせっかく受け取った過払い金、できれば税金を払いたくないと思う人も多いはずです。果たして、申告しなくてもバレない方法はあるのでしょうか?
もし申告しなければどうなるのか、少しでも税金を抑える方法はあるのか、などあわせてご紹介していきます。
過払い金の税金を払わないと税務署にバレる?
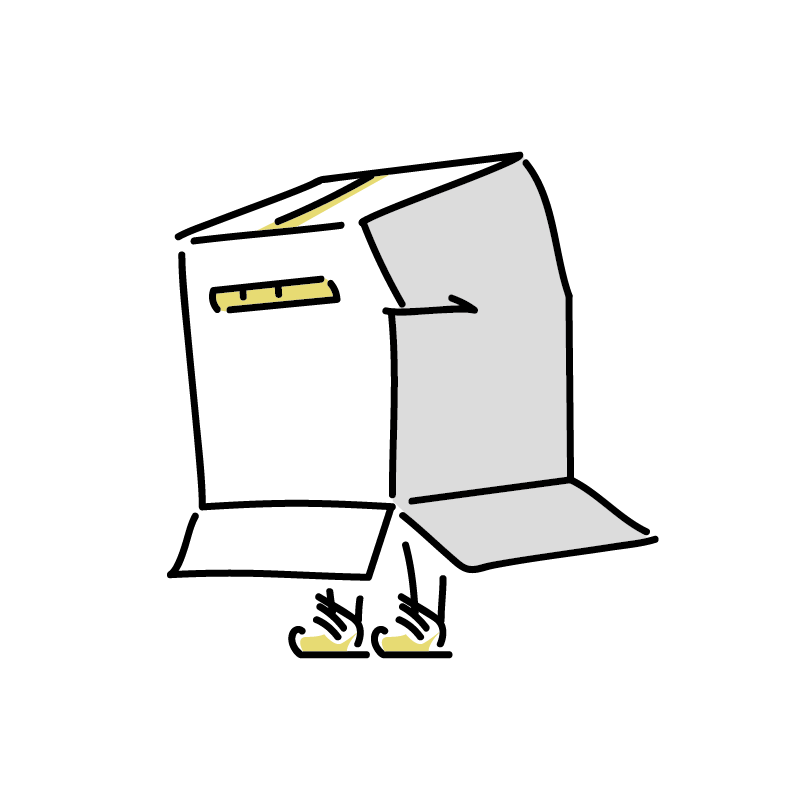
結論からいうと、過払い金の税金を払わないとバレる可能性が充分にあります。というのも所得税は申告税なので、即座に税務署にバレるということはありませんが、以下のようなことがあると、申告していないことがわかってしまいます。
- 個人の口座に大量の入金があった
- 仕事の関係者、知人などが税務署にタレコミをした
- 過払い金請求を依頼した事務所に税務調査が入った
- 税務調査がきた
このような事実をきっかけに、税金を払っていないことが明らかになるのです。
また国税局では社会的な注目や関心の高い事案に対して集中的な調査を行うこともあり、実際に過去には「過払い金請求」における申告漏れの調査がされたこともあります。
中央事務所は、過払い金など借金問題に特化した最大手の司法書士事務所です。
<特徴>
・テレビやラジオでのCMや口コミをきっかけに多くの人に利用されている。実績が多く過払い金のさまざまなケースに対応してきたノウハウがあり、家族にバレないプライバシー対策も厳重。
・相談料・着手金が無料なので、過払い金が返ってこない限りは費用が掛からない仕組み。
中央事務所は、損をしたくない方やスムーズに過払い金を終えたい方におすすめ。

中央事務所の無料診断は、診断した後に過払い金が発生していたらそのまま無料相談を予約することも可能です。
全国各地で出張面談が実施されているので、ご自宅の近くで過払い金や借金問題に対する不安を相談することができます。中央事務所 ホームページ
過払い金を申告しなければいけない人
過払い金には税金のかかるケースとかからないケースがあります。では税金のかかるのはどのような場合なのでしょうか?
利息も含めて取り戻した場合
過払金は請求する際、5%の利息をつけて取り戻すことができます。この利息分は自分が支払ったお金ではないので、雑所得とみなされ税金がかかります。
ただし1年間の雑所得の合計が20万円を上回らない場合は申告不要です。つまり過払い金の利息以外に申告する雑所得がなく、金額が20万円以下であれば申告なしで問題ありません。
利息の支払いを経費として計上していた場合
借り入れの返済利息を確定申告で経費に計上していた場合、税金がかかります。経費として所得から控除していたものが戻ってきたので、申告よりも所得が増えたという考え方です。ただしこの場合は、以前から確定申告をしていたことが前提になります。通常は申告の必要のないサラリーマンや主婦ではなく、自営業やフリーランスの人が当てはまります。
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合、利息だけでなく元金も一時所得とみなされ税金がかかります。生活保護では給与はもちろん年金や預貯金も収入とみなされます。もしそれらの収入の額が大きくなると、生活保護の減額調整や受給停止になるので注意しましょう。
過払い金の税金を払わないでバレるとどうなる?
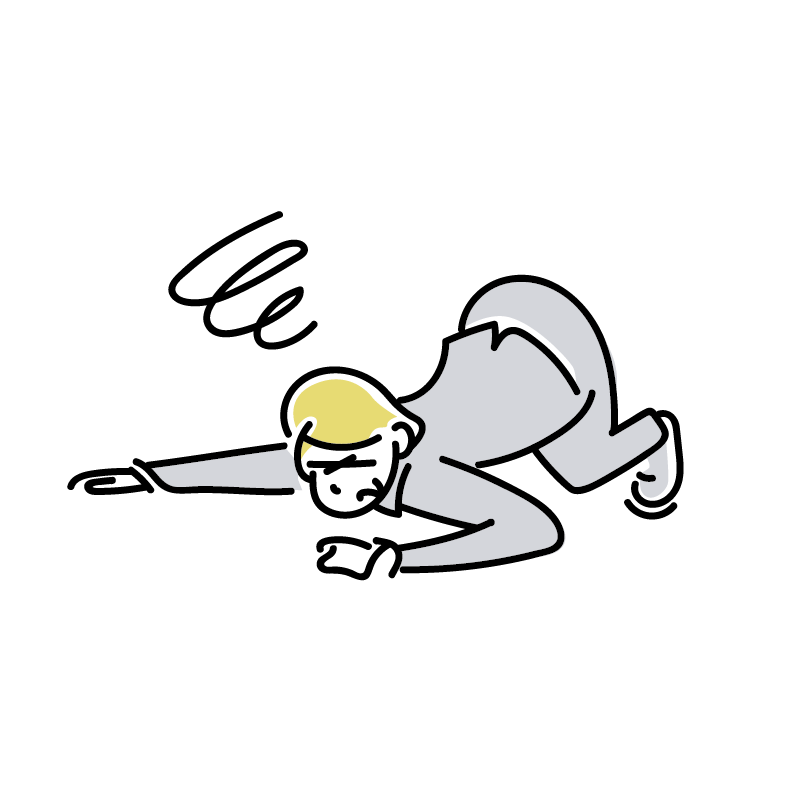
過払金の税金を支払わないと延滞税や無申告課税などのペナルティが科せられることがあります。悪質なときには懲役刑など重い罪になる可能性もあるので、正しく申告することをおすすめします。
どうなるか① 無申告加算税が発生する
無申告加算税とは、確定申告をしなかった場合や期限後申告をした場合に納税額に応じて課される税金のことです。
| 納税額 | 税率 |
| 50万円まで | 15% |
| 50万円を超える部分 | 20% |
例えば納税額60万円が無申告だった場合、50万円×15%+(60万円-50万円)×20%=95,000円
95,000円の無申告加算税を納めなければなりません。
ただし期限後であっても税務調査が入る前に自主的に申告した場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。この場合納税額が60万円の無申告加算税は30,000円です。
また確定申告の期限が過ぎていても、「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」、「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」など一定の条件をすべて満たせば、無申告加算税は課されません。
どうなるか② 延滞税が発生する
延滞税とは、税金が期限内に納付されなかった場合に課される税金です。期限後申告をすると、納期限の翌日から申告書を提出した日までの日数に応じて課税されます。延滞税は国が計算するので納税者が計算する必要はありませんが、原則として納期限の翌日から2カ月間は「7.3%」か「特例基準割合+1%」、納期限の翌日から2カ月を経過した日以後からは「14.6%」か「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合になります。年分ごとに異なりますが、例えば令和3年分は納期限翌日から2カ月は年2.5%、2カ月以降は8.8%です。納税額が50,000円だったとすると、2カ月までは1,250円、2カ月以降は4,400円ということになります。
どうなるか③ 単純無申告ほ脱犯となる可能性もある
「ほ脱」とは不正な手段によって税金を納めないこと、要は「脱税」です。平成23年の税制改正により「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設され、故意に脱税をした場合に「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」という重い刑罰が科されるようになりました。
また脱税をするつもりはなく単純に申告や納税を忘れていた場合にも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。脱税は重大な犯罪です。少額の納税を惜しんだばかりに、大きな代償を払わなければならないことをよく理解しておきましょう。
過払い金の税金をバレない方法はある?
過払いの税金をバレない方法があるとすれば「無申告にして後はバレないことを信じて運まかせ」にするのみです。税務署は無申告がわかっていてもすぐに調査を行うわけではなく、何年かして突然調査にやってくることがよくあります。つまり無申告はバレていないのではなく「税務署がまだ調査に来ていないだけ」なので、後になってかなり高い確率でバレてしまいます。
繰り返しになりますが、故意の脱税は犯罪です。これだけは忘れないようにしましょう。
弁護士費用を経費とすることで、税金を抑えることはできる
確定申告で弁護士費用を経費すれば税金を抑えることができます。ただし経費にできるかどうかは管轄の税務署の考え方によって違います。ここでは経費にできることを前提にして説明していきます。
弁護士費用を経費にできる場合、過払い金の利息にかかった割合分だけ経費にすることが可能です。
例えば、過払い金が元金270万円と利息30万円、弁護士費用が60万円(過払い金元利合計の20%)だった場合、
過払い金の利息にかかった弁護士費用の割合は利息30万円÷(270万円+30万円)×100%=10%
経費に算入できる弁護士費用は、60万円の10%なので6万円になります。よって利息60万円に対してかかる税金は、弁護士費用を差し引いた54万円(60万円-6万円)に対して計算されることになります。
過払い金を申告すると税金はどれくらい取られる?
所得税の税金計算は下記の方法で計算できます。
所得税=課税所得額×所得税率-所得税率表の控除額-税額控除
このうち過払金の利息は課税所得額に算入されます。しかし過払い金を申告したときの税金の額は、利息の金額やご自身の収入、医療費控除などで変わってくるので一概に「どのくらい」とは言えません。
例えば40代(扶養なし)年収300万円で過払い金の利息が100万円、過払い金以外に申告するものがない場合だとすると、
| 支払い金額 | 3,000,000円 |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 2,020,000円 |
| 所得控除後の合計額 | 912,000円 |
| 源泉調整額 | 56,500円 |
| 社会保険料等の金額 | 432,000円 |
確定申告で納めなくてはいけない税金の額は98,700円(復興特別所得税額含む)になります。
複雑に感じますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーというサイトを利用すれば、税額を簡単に計算することができます。(国税庁の確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)
過払い金の申告の仕方
ここでは確定申告をする機会の少ないサラリーマンの確定申告の流れをお伝えしていきます。確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。
必要な書類を揃える
まずは確定申告書に必要な書類を揃えていきます。
必ず必要な書類
- 確定申告書A様式
- 源泉領収表
- 預り金清算書など、過払い利息金と弁護士費用がわかる書類
必要に応じて必要な書類
- 医療費控除の明細書
- 寄附金受領証明書 など
確定申告書類を作成する
手書きと手計算で作成する方法もありますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば簡単に作成することができます。
またご自身での作成が面倒な場合は、税理士に依頼するのも手段の一つです。ただし税理士へ依頼するには、3万~15万円ほど費用がかかります。過払い金の申告に複雑な計算は必要ないので、税理士に依頼するのはもったいないかもしれません。
確定申告書を提出し、納税する
税務署に確定申告書を提出します。提出方法は、「税務署に直接持参する」「e-Taxを利用する」「税務署へ郵送する」の3つがあります。申告時期の税務署は大変混み合っているので、e-Taxか郵送で送ることをおすすめします。確定申告書の提出が終わったら、納税しましょう。所得税の納期限は毎年3月15日です。
過払い金請求でおすすめの事務所とは
過払い金請求ができる弁護士・司法書士事務所はたくさんあり、どれも同じように見えますよね。
しかし、安易に事務所を選んでしまうと、途中で信用できなくなったり損する結果になったりして、嫌な思いをする可能性もあります。
そこで、損するリスクを回避して、スムーズに過払い金請求をするための事務所選びのコツを2つご紹介します。
過払い金に特化した事務所を選ぶ
過払い金請求や借金問題を専門的に扱う事務所は、回収金額や解決案件数の実績が豊富です。
蓄積されたノウハウがあるので、戻ってくる過払い金の金額が多い傾向にあり、さまざまなニーズに柔軟に対応してくれます。プライバシー配慮なども厳重に行ってくれます。
経験豊富だと「相談しやすい」と感じるかたも多いでしょう。
初期費用なしの事務所を選ぶ
もし請求したのに過払い金が返ってこなければ、手持ちから相談料と着手金を払う必要が出てきます。
そうならないため、初期費用(相談料と着手金)が無料の事務所を選びましょう。過払い金が返ってこない限り、費用は発生しません。
無料相談はちゃんとしていないんじゃないか?と心配になる方もいるかもしれません。しかし無料相談とはいえ、実際に利用した人の声をきいてみると有料の相談と比べて遜色ありません。
おすすめの事務所3つ
過払い金請求の実績が豊富で、初期費用が無料の事務所のなかで、おすすめの事務所を3つ紹介します。
| 事務所名 | 実績 | 専門性 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
東京ロータス法律事務所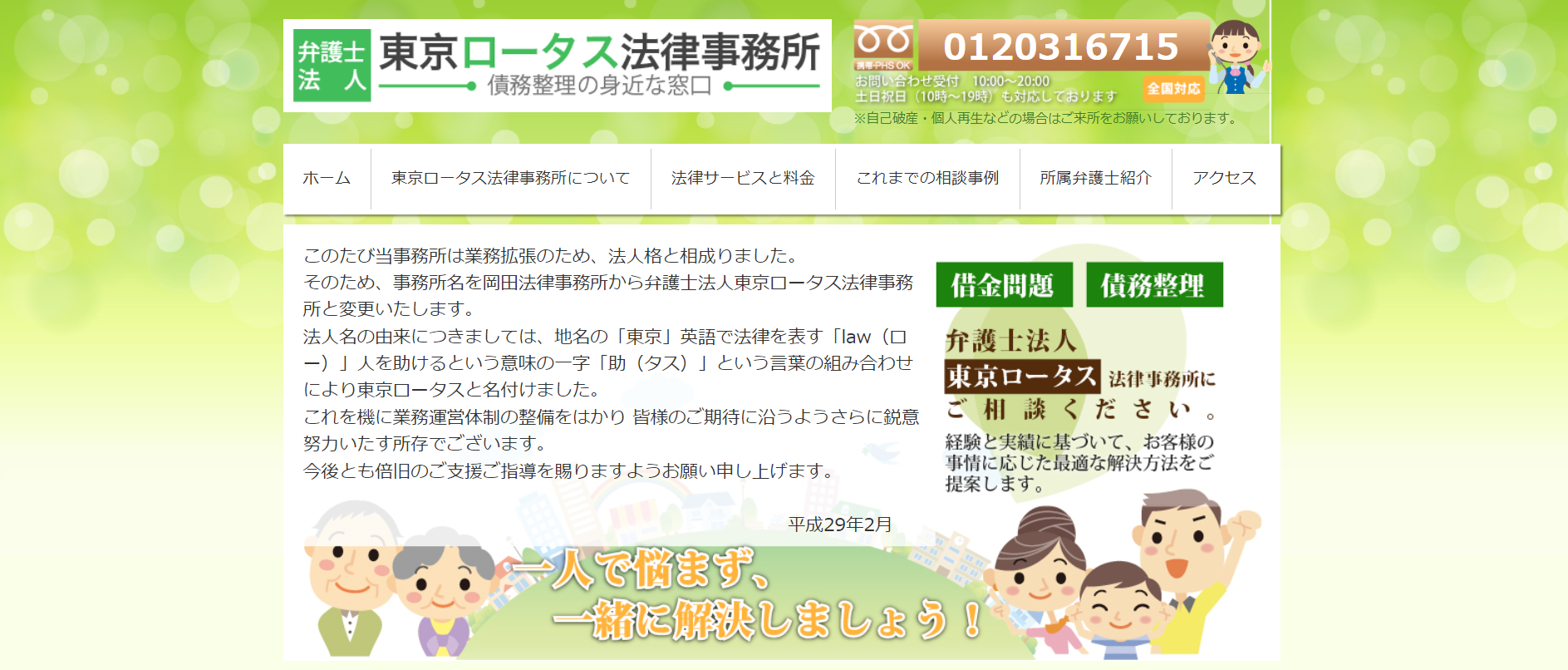 ロータス詳細ページへ | 〇 受任件数 7,000以上 | ◎ 専門性高め | ◎ 無料 |
ひばり法律事務所 ひばり詳細ページへ | 〇 事務員と弁護士 がベテラン | ◎ 専門性高め | ◎ 無料 |
アース法律事務所 詳細ページへ | 〇 受任件数 3,500以上 | 〇 幅広く取り 扱う事務所 | 〇 無料(相談無料 は初回のみ) |
記事まとめ
過払い金にかかる税金の解説をしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
過払い金の税金は申告しなくてもすぐにバレるわけではありませんが、バレたときには無申告加算税や延滞税を払わなければならないだけでなく、故意の脱税とされた場合には重い刑罰が科されます。
過払い金の税金を抑える唯一の手段は「正しく申告」することです。いつバレるか不安な日々を過ごすくらいなら、正しく申告・納税してすっきりしてしまいましょう。